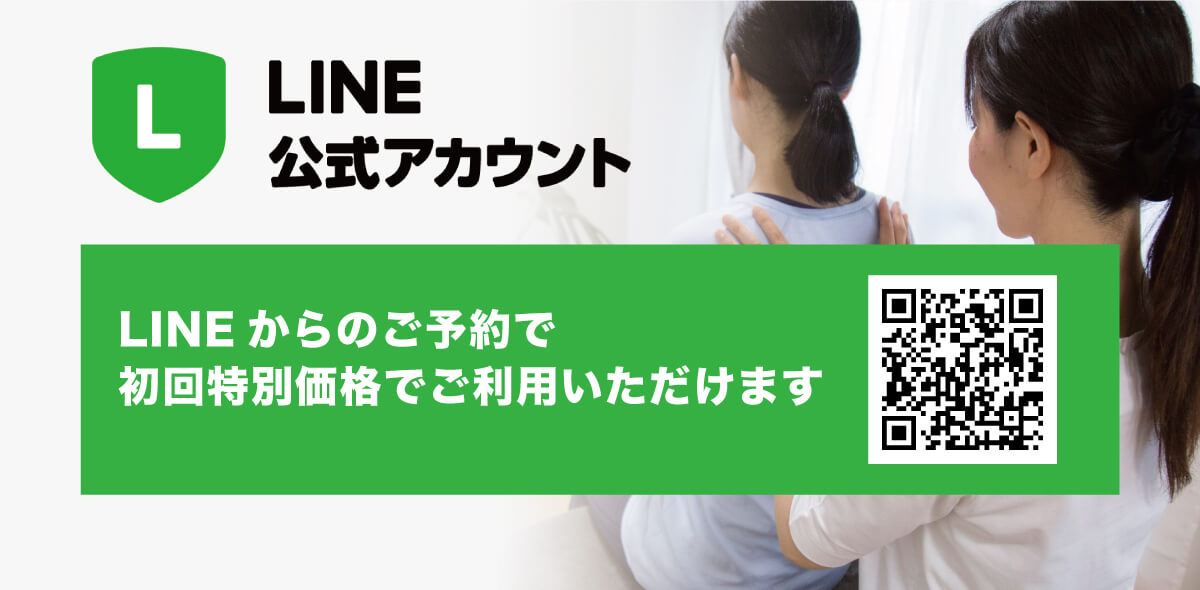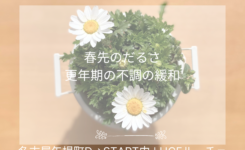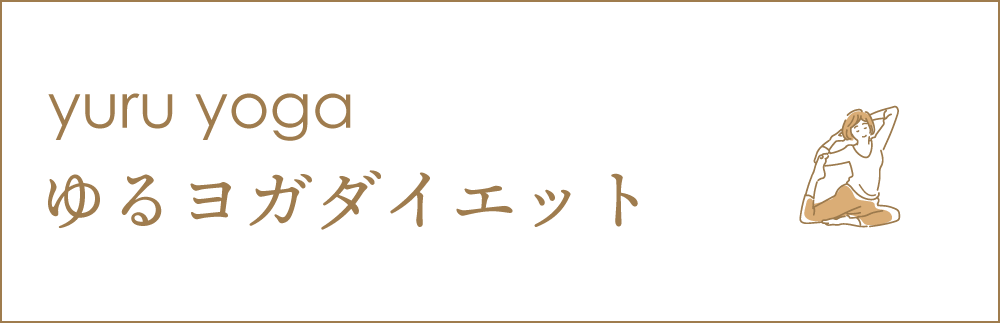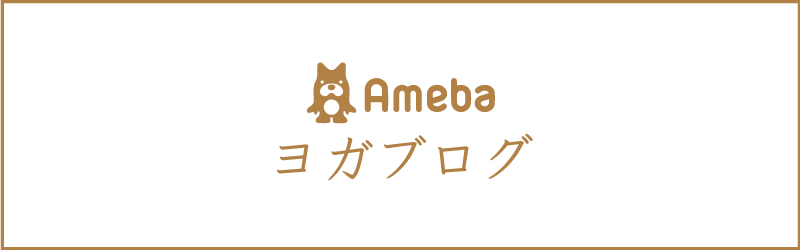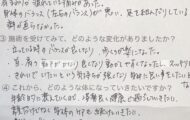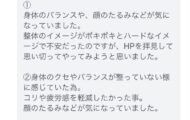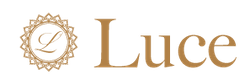養生とは病気になってからの治療法ではなく、病気になる前の予防法です。
季節に応じて心身を調和させるのが養生法ということになりますね^^
冬の養生法
東洋医学では冬は「腎」の季節といわれています。
西洋医学の「腎臓」とは少し考え方が違いますが、腎は加齢や老化に関わり、年齢を重ねた私たちにはとても重要な臓器です!!
腎のはたらきが弱くなると、
体力・免疫力の低下、
疲労感、冷え、
腰痛、足腰が弱くなる、
呼吸が浅くなる、
骨や歯が弱くなる、
健忘症、めまい、
髪、耳、水分代謝や尿のトラブル、など
老化現象ともいえる症状があらわれるようになるといわれています。
寒さに弱い腎は冷えると機能が衰えやすくなるので温めることが大切です。
腎は「腰」にあたるので、背中や腰、足元を冷やさないようにして、筋力をつけたり姿勢にも気をつけると◎
腰や背中の冷えやコリ、張りをそのままにしておくと不調にもなりやすいので、辛くなる前に解消していきましょう!
寒くなると老廃物をため込みやすくなりますので、巡りのよい体で過ごしたいですね。
冬の養生ヨガ
腎は冷えると働きが悪くなると言われていますので暖めることが大切!^^
場所は「腰」を温めるのですが、腰には「腎兪(じんゆ)」というツボがあります。
ちょうどウエストの一番くびれているライン、背骨の両側、指2本分外側にあります。
この下には腎臓があるといわれ、腰痛、腰の冷え、むくみ、全身の冷えなどに効果があるツボです。
このツボを押したり、マッサージをして刺激したり、身体をねじるポーズや腰や背中を伸ばすポーズ、腰回りに効くポーズで気血の巡りをよくして腎の働きを高めます。
また「腎経」という「経絡(けいらく)<気血の流れるルート>」のツボで足の裏にある「湧泉」は、冷え、のぼせ、むくみ、疲労回復などに効果があります。
湧泉を刺激したあとはさらに、「腎経」が通る足の内側を伸ばしたり刺激をするポーズを行うことで気血の巡りをよくします。
腎のはたらきが弱くなると呼吸も浅くなるので、お腹を使う「腹式呼吸」で深い呼吸をし腎を元気にしましょう!
最後にプチ薬膳^^
腎を元気にする食養生は
(黒いもの)黒豆、黒ごま、黒米など、
(身体を温めるもの)ニラ、ショウガ、シナモン、海老など
(鹹味<自然のしょっぱさ>のもの)海苔、昆布などの海藻類
などを、ほどよくいただくこと。
寒い季節、どうしても身体を動かすのが億劫になりがちですが、健康のため、エイジングケアのためにも心地よいヨガで身体を整えましょう^^